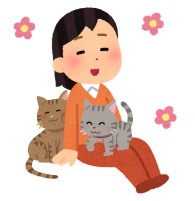
こんにちは!こんばんは!クロネコあぐりです。
この記事ではこんなことに触れています。
- 猫が「ふみふみ」や「すりすり」をする意味と効果・効能について
猫の「ふみふみ」や「すりすり」、飼われている方なら一度は経験したことあるんじゃないでしょうか?
「あれって、悪魔的なカワイさですよね!」
え?されたことない?
もったいない! 猫を飼っているからには1度はされた方がいいですよ!!
ふみふみやすりすりをしているときの猫はまさに天使です!(どっちなんだ笑)
ただ、あの行動をする意味ってみなさん知っていますか?
猫のほうも何の意味もなしにあんなに一心不乱にやってません。
する意味とすることで得られる効果・効能があるんです。
ということで今回は
- 猫の「ふみふみ」には何の意味があるの?
- ふみふみに含まれる5つの効果・効能
- ふみふみする猫としない猫がいるのはどうして?
- 猫が「すりすり」をしてくるのは何の意味?
- すりすりの仕方からわかる猫の気持ち
といったことについて解説させていただこうかなと思います。
これを読めば、あなたもふみふみやすりすりをお返ししてあげたくなるはずです。
- 猫の「ふみふみ」には何の意味があるの?
- ふみふみに含まれる5つの効果・効能
- ふみふみする猫としない猫がいるのはどうして?
- 猫が「すりすり」をしてくるのは何の意味?
- すりすりの仕方からわかる猫の気持ち
- まとめ
猫の「ふみふみ」には何の意味があるの?

「猫のふみふみ」
一心不乱にやっていたかと思えばコテンと眠りに落ちてしまう。
寝る前にいつもやっているようだけど、何の意味があるのでしょうか?
ただただあなたに「甘えていたい」

もともとあのしぐさは
子猫が母猫からおっぱいをもらうときに、ふみふみしていっぱい出てくるようにするためのしぐさ
なんです。
ふみふみする猫をよく観察すると、手を開いたり握ったりして揉んでいるようなしぐさをしているのがわかると思います。
なので、大人になった猫には本来必要のないしぐさなんです。
でも、大人になってからもふみふみしている猫っていっぱいいますよね。
それは「子猫のときの名残」で、やわらかくてフワフワしたものに触れると、
母猫に包まれていた時の安心感や心地よさを思い出し、思わずふみふみしてしまっている
と言われています。
つまり、猫がふみふみをする意味とは
「甘えていたい」
ということです。
猫があなたの体の上でふみふみし始めたら、思いっ切り甘えさせてあげましょう。
「発情期のサイン」でもある

普通は「前足」を使ってふみふみをしていると思うのですが、これを「後ろ足」でやっていた場合は
「発情期に入っているサイン」
となります。
去勢・避妊手術をしていない猫にみられるふみふみで、同時に腰をカクカクと動かすようなしぐさもします。
交尾したくてもできないような状態が続くと、猫にとって大きなストレスを抱えるようになりますので、子猫を生ませる予定が無いのであれば「去勢・避妊手術」をすることをオススメします。
その方が、猫も長生きしやすいですしね。
「去勢・避妊手術について時期やかかる費用」など、こちらで解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
ふみふみに含まれる5つの効果・効能

猫のふみふみは他にも「にぎにぎ」や「ぐーぱー」などとも呼ばれ、英語では
「kneading(ニーディング)」「milk tread(ミルクトレッド)」と言われています。
その効果・効能にはいくつか種類がありますので、解説していきましょう。
心から安心できるリラックス効果

子猫のときの母猫のお腹でおっぱいを飲んでいた”心地よさ”や”安心感”といったことを思い出しているので、リラックスできる効果があります。
中にはリラックスしすぎて”心ここにあらず”の状態になってしまい、よだれを垂らしてしまっている猫もいるくらいです。
飼い主さんの体でするようなときは、甘えています。
お腹の上でするようだと、お腹の肉がぷよぷよで気持ち良いと思われていることも(笑)
夢の世界へと誘う

何も考えず一心不乱にやりながらリラックス効果もあるため、
だんだんと眠気を誘ってきます。
ふみふみを始める
↓
目がトロンとして閉じていく
↓
ふみふみの速度が遅くなっていく
↓
そのまま眠りに落ちてしまう
といった流れになることが多いです。
子猫なんかだと眠ったままふみふみの動作をしていることも(笑)
気持ちが落ち着いてよく眠れるため「寝る前のルーティンワーク」としている猫もいるみたいです。
「自分のものです」アピール

猫は足の裏にも「臭腺」というニオイを出す器官があります。
この器官で、ふみふみをしながらニオイをつけ、
「これは自分のものだ」と周りにアピールする意味があります。
飼い主さんに対してする場合も自分のニオイをつけて
「この人は自分だけの大切なものなんだ」
とアピールしているということです。
ただ、他にも「自分の方が上だ」とアピールする”マウンティングの意味”もあったりするようなので、どちらの意味でやっているかは...ご想像にお任せします(笑)
ストレスや不安を解消させる

気持ちを落ち着かせリラックスの効果があるため
ストレスや不安を解消しようとしているときにもふみふみをすることがあります
が、この場合は”注意が必要”です。
そういった場合には
毛布やタオルといったものを吸ったり、かじったりしながらやっていないでしょうか?
これは
「ウールサッキング」と呼ばれる行為で”猫の異食行動”のひとつです。
見た目にはとてもカワイイのでそのまま見ていてしまいそうですが、
毛布やタオルの欠片、繊維などを猫が飲み込んでしまうおそれがあります。
飲み込んだものが吐き出されればまだいいですが、腸に絡まったり詰まったりして
「腸閉塞」
を起こしてしまう可能性が高い行動です。
ウールサッキングを見かけた場合は、すぐに止めさせましょう。
そして、繰り返さないように原因となっているもの(ストレスや不安を感じているなら何に対してか)を突き止め、排除してあげましょう。
ほんわかと癒されて時間のたつのも忘れて見てしまう

これは飼い主さんに対する効果・効能でしたね(笑)
ふみふみを自分のところに来てされると、カワイ過ぎてこっちまで癒され抜群のリラックス効果を発揮してしまいます。
思わず撫でたり、ギュッとしたりしてしまいそうですが、
猫の方は集中して一心不乱にやっているので、ジャマしないようにしてあげましょう。
また時間のたつのも忘れて見入ってしまうため、用事がある場合には気をつけてくださいね(笑)
ふみふみする猫としない猫がいるのはどうして?
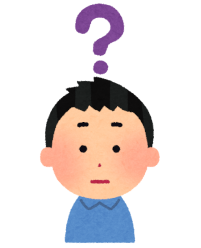
すべての猫がふみふみをするように思われているかもしれませんが、決してそうではありません。
中には、一切ふみふみをしない猫もいます。
子猫のときにしっかりと親離れができている場合はふみふみをしなくなるようです。
母猫は子猫が固形物を食べられるようになってくると「乳離れ」を促し、子猫がふみふみをしてきても追い払うようになっていきます。
そのため子猫はふみふみをする理由がなくなるので、次第にしなくなっていくということです。
逆に何歳になっても、甘えるときにふみふみをするような猫は親離れが早かった可能性があり、幼児性がなくならないことが多いです。
また「猫の性格」によっても違いがあらわれ、
自分に自信があって強い猫はふみふみをしない
傾向にあると言われています。
ふみふみをするかしないかで何か異常があったりするわけではないので、
する猫には思う存分させてあげ、しない猫には他のやり方で甘えさせてあげましょう。
猫が「すりすり」をしてくるのは何の意味?

猫が不意にしてくる「すりすり」
こちらの顔を見上げながらされた日には、可愛くてどうしようもなくなること間違いなしですが、あの行動には何の意味があるのでしょうか?
猫がすりすりに込めている意味を1つずつ詳しく解説していきましょう。
安心できるのが一番だよね!
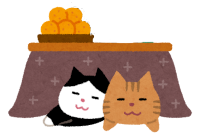
まずは”安心”と言う意味です。
猫は警戒心が強い動物。
少しでも知らないニオイがあると安心することができません。
家の中など自分の縄張りに知らないニオイが出てきたときは、
”すりすり”をして自分のニオイをつけて安心を得ようとします
ただ、すりすりは
「スプレー行為(オシッコによるマーキング)」
「爪とぎ」
といった他のマーキングと比べてニオイの持続時間が短いため、毎日のように縄張りをパトロールしてニオイをつけ直すようにしています。
そのため、毎日服を着替えたりお風呂に入ってニオイを変えてしまう「飼い主さん」は、そのたびにニオイをつけ直さなければいけないので大変なんです。
そうして周りがすべて自分の知ったニオイになると、安心して眠ったり毛づくろいをしたりするようになるんです。
仲のいい猫、人にあいさつをしてます

次に”あいさつ”という意味です。
猫のすりすりは
仲のいい猫同士や人に対してのあいさつの意味もあります
「気を許している相手にニオイをつけると同時に相手のニオイを確認している」
と言われています。
この、”あいさつのすりすり”は
やっている時間が長ければ長いほど友好的な関係を築いている
と言われていますので、飼っている猫がすりすりすりすり...といつまでもやっていたとしても
「長い!いつ終わるんだろう?」
と思わずに、
「そんなに仲良しだと思ってくれているんだ」
と捉えて、気が済むまですりすりさせてあげましょう。
あなたへアピールしたい

最後に”アピール”という意味もあるようです。
猫のすりすりは
あなたに「何かをしてほしい」とアピールしている場合もあります
- 「あなたにかまってほしいとき」
- 「ごはんが欲しいとき」
- 「トイレを掃除してほしいとき」
- 「もっと撫でてほしいとき」
- 「甘えたいとき」
といった場合に「早くして!」という感じでアピールしているようです。
これは、以前”すりすりしたことで自分の要求がかなった”といった経験のある猫が
「すりすりすればやってもらえるんだ」
と学習し、”要求をかなえるための手段”としてすりすりしているとも考えられます。
すりすりの仕方からわかる猫の気持ち

猫のすりすりにはいくつかのバリエーションがあり、その違いで
今どういう気持ちなのかがある程度わかります。
ケース別のすりすりの気持ちについてまとめてみましたので解説していきたいと思います。
ちなみに猫が気持ちを表現する他の方法についてはこちらで解説しています。
参考までにご覧になってみてください。
足にまとわりつくようにすりすりしてくる
猫が足にまとわりつくようにすりすりしてきて、
「嬉しいけど歩きにくいんだよな~」
といった状況になったことありませんか?
まとわりつくようにしてきた場合は
「不安感や寂しさを感じていてあなたに甘えたい」
と思っているときです。
足に絡まるようにまとわりついて全身の”臭腺”を使い、自分のニオイをたっぷりつけて安心したいんです。
特に、あなたがどこかに出かけていて帰ってきたときにすることが多くないでしょうか?
長い時間留守番をしていて、寂しくてたまらなかった思いを爆発させているんですね。
「おかえり~、寂しかったんだから構って!」
といったところでしょうか(笑)
顔や頭を押し付けるようにすりすりしてくる
くつろいでいると猫が寄ってきて急に頭をゴツン。
「何だ?」
と思っているとその後も何回も押し付けるように頭突きをしてくる。
そんな経験ないですか?
この「猫の頭突き」は意外と勢いよくされるので
「嫌われてるのかな?」
と思ってしまいそうですが、じつは正反対の意味なんです。
猫のおでこ付近には自分のニオイをつける「臭腺」があって、あなたに自分のニオイをつけようとしています。
この
「猫が顔や頭を使ってニオイをつける行動」
は自分にとって大切な人や物に対してする行為だそうです。
また猫の間では
”自分より地位が上の猫にしかやらないすりすり”
と言われています。
つまり、
「あなたを最も信頼し、大切に思っている」
ということになります。
おめでとうございます!良かったですね!!
家具などに全身をこすりつけるようにすりすりしている
家具などの角に、しきりに全身をこするつけるようにすりすりしているようなこと、ありませんか?
そんな場合は、
特に不安や甘えたいという気持ちはないけど、周りのものすべてが自分のニオイじゃないと安心できない。
つまり、
「この周りにあるものは全部が自分のものなんだからね!」
といったアピールのようなものです。
そのため、お尻の方まで使って入念にニオイをつけているんだと思います。
もちろん、その”全部”の中にはあなたも含まれていると思いますよ。
まとめ
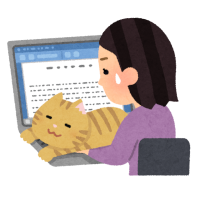
いかがだったでしょうか。
今回は「猫のふみふみとすりすり」についていろいろ解説させていただきました。
今回のまとめとしては
- 猫がふみふみをするのは子猫のときの名残でもともとは母乳を出しやすくするための行動
- ふみふみで得られる効果・効能として「リラックス」「眠気を誘う」「ストレス・不安解消」「マーキング」「飼い主が癒される」といったものがある
- ウールサッキングをしている場合はすぐに止めさせるようにする
- 猫のすりすりは「安心」「あいさつ」「アピール」の意味がある
- すりすりのやり方の違いでそのときの気持ちがある程度わかる
といったところでしょうか。
「ふみふみ」や「すりすり」しながら甘えられると可愛らしくてしかたないですよね。
ただし、服や毛布などがほつれたり穴が開いたり、毛まみれになってしまうかもしれませんが、それは自己責任で(笑)
それでは、この記事が少しでもあなたの参考になったなら幸いです。