
こんにちは!こんばんは!クロネコあぐりです。
この記事ではこんなことに触れています。
- 飼い猫の妊娠から出産までで飼い主にできること
- 猫の出産後に気をつけたい病気や症状
「うちの猫が妊娠したとき、何かできることあるんだろうか?」
多分、自分を含めけっこうな飼い主さんがそう思うことだと思います。
経験したことがないと人間の場合でもわからないのに、ましてや猫の場合なんてホントにわかりませんよね。
猫は安産な動物ということで、出産するときはあまり手を出さない方がいいと言われています。
「じゃあ、してあげれることってないのかな?猫の好きにさせておいたらいいのか?」
・・・って言っても、やっぱり何かしてあげたいですよね!
そこで今回は
- 飼い猫が妊娠したときに飼い主ができること
- 飼い猫が出産するときに飼い主ができること
- 飼い猫が出産した後に気をつけたい病気や症状
について紹介と解説をさせていただこうかなと思います。
妊娠・出産に対して知識と準備を万全にし、飼い主のありがたみを見せつけてやりましょう。
飼い猫が妊娠したときに飼い主ができること

飼い猫が妊娠していることがわかったときに、飼い主がしてあげれることって何があるでしょうか?
飼い猫のお腹に宿った小さな命、
母子ともに健康であるために妊娠時における飼い主さんの役割はけっこう大きいです。
すべての準備を万全にして、一抹の不安もなくその日を迎えられるようにしたいですね。
飼い猫が妊娠したことに気づいたら、動物病院で診察を
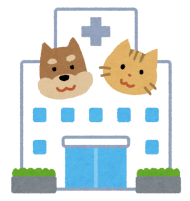
妊娠に気づいたら、まずは動物病院で診察を受けましょう。
妊娠初期の段階では気づきにくいこともあるので、お腹も膨らんできたころ(30日~40日前後)に行くようになると思います。
動物病院では、
- 「何匹の子猫が生まれるのか」
- 「健康状態はどうなのか」
を調べてもらいましょう。
生まれてくる子猫の数がわかっていれば、出産時に全部生まれたかどうかの判断がしやすくなります。
妊娠中はエネルギーが必要なので妊娠の段階に合ったごはんに変える

妊娠の初期段階では今までと同じごはんで問題ないですが、妊娠後期(40日前後)になったころから、
お腹の中の子猫を育てるために普段より約2倍のエネルギーが必要になってきます。
猫自体も食欲が増してくると思うので、
「高たんぱく、高脂質、高カロリー」
のものを食べさせてあげましょう。
ただし、あげ過ぎて肥満になってしまうと難産の原因になったりするので、猫の状態を見て適切な栄養管理をしてあげましょう。
「ピュリナワン 1歳までの子ねこ用 妊娠・授乳期の母猫用」
2,2㎏(550g×4袋)/1,609円(Amazon)
こちらは、たんぱく質40%以上、脂質18%以上、カロリー440kcal/100gとなっている、栄養バランスに優れたキャットフードです。
味はチキンとまぐろがあります。
体重 分量
2㎏ : 30g
3㎏ : 40g
4㎏ : 55g
5㎏ : 70g
6㎏ : 80g
7㎏ : 95g
を1日2回に分けてあげましょう。
※目安の量なので、猫の体調などを見て適切な量にしてください。
「ヒルズ サイエンス・ダイエット キャットフード キトン 1歳まで健康的な発育をサポート 子猫/妊娠・授乳期」
1,8㎏/1,835円(Amazon)
こちらは、高品質の魚油由来のDHAも含まれているので、脳や目の健康にも良いキャットフードです。
味はチキンとまぐろがあります。
たんぱく質35%以上、脂質21.5%以上、カロリー425kcal/100gとなっています。
体重 分量
2㎏ : 55g
3㎏ : 75g
4㎏ : 95g
5㎏ : 110g
6㎏ : 125g
7㎏ : 145g
をあげるようにしましょう。
※量は目安なので猫の体調などを見て適切な量にしてください。
「ロイヤルカナン FHN-WET マザー&ベビーキャット」
24個入り13,500円(Amazon)
こちらは、食べやすいムース状になっていて嗜好性も高いウェットタイプのキャットフードです。
こちらのキャットフードはドライタイプもあります。
たんぱく質8.5%以上、脂質3.5%以上、カロリー96kcal/100gとなっています。
妊娠期の母猫 : 2~5パック
授乳期の母猫 : 食べるだけ
を1日2~3回に分けてあげましょう。
また、ドライフードもあげる場合は
妊娠期の母猫 : 1パックと27g~101g
授乳期の母猫 : 食べるだけ
を1日2~3回に分けてあげましょう。
※量は目安なので、猫の体調などを見て適切な量に調節してください。
安心して出産ができるような環境づくりをしてあげる
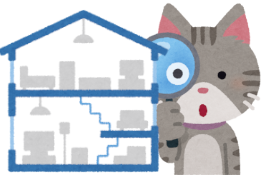
妊娠後期になって子猫の胎動なども感じれるようになってきたら、
安心して出産ができるように環境を整えてあげましょう。
母猫が中である程度動けるくらいのダンボールや箱を用意して「産箱」をつくってあげましょう。
中には、普段使っているタオルや毛布を敷いてあげてください。
置く場所としては猫が落ち着ける場所、少し暗くて人があまり来ないようなところが良いですね。
また、猫の出産は夜になることが多いので、
事前にかかりつけの動物病院へ連絡しておくか、夜間対応可能な病院や、救急対応可能な病院を調べておきましょう。
飼い猫が出産するときに飼い主ができること

いざ飼い猫が出産するときに、私たち飼い主には何ができるのでしょうか?
「出産」という一大イベント!
できることがあるなら何でも協力してあげたいところですね。
基本的には母猫にすべてを任せ手を出さずに見守る
いきなり出鼻をくじいてしまいました(笑)
猫の出産では基本的には飼い主さんがあれやこれやと手を出さない方がいいです。
あまり出産のときにかまい過ぎたりすると、
猫も落ち着いて出産できませんし、必要以上に子猫に触れたりすると母猫が子猫の世話をしなくなったりします。
「何かトラブルが起こったようなときだけサポートしてあげる」
といったスタンスで見守っておきましょう。
難産など何かトラブルがあった場合は動物病院へ連絡する
出産中に
難産など何かのトラブルがあった場合は、すぐ動物病院へ連絡するようにしましょう。
そして、獣医師の先生の指示を仰ぐようにしてください。
私たちのような素人の飼い主はホントにサポートくらいのことしかできません。
下手に手を出すと逆に母猫や子猫を危険にさらしてしまう可能性もあります。
ただし、子猫を生んだ後、母猫が羊膜を破ったりしないようならサポートしてあげなければいけません。
その場合にすることは
- 羊膜を破る
- へその緒を糸で縛る
- へその緒を切る
- 子猫を軽く振って、鼻や口に入っている羊水を出す
その後、子猫をタオルで拭いてあげて、呼吸を促します。
呼吸を確認したら母猫のところへ戻してあげましょう。
母猫が子猫を潰さないように注意して見ておく
出産をしているとき、母猫は落ち着かずにいろいろと体制を変えながら出産していくことがあります。
その際、
子猫を踏んでしまい押しつぶしてしまうといった事故が起こる
こともあるようです。
生まれたばかりの子猫は小さくて繊細です。
すべてが終わるまでは注意深く見守ってあげるようにしましょう。
飼い猫が出産した後に気をつけたい病気や症状

飼い猫が無事出産を終えて、ホッと一息つきたいところですが、
猫の出産後には母猫の体調に気をつけておいてあげましょう。
出産にはエネルギーを使うので、体調を崩したり出産後特有の病気にかかってしまうことがあります。
出産後に出ることがある症状や病気は
- 異常な出血
- 子癇(しかん)
- 子宮内膜炎・子宮蓄膿症(しきゅうないまくえん・しきゅうちくのうしょう)
- 産褥熱(さんじょくねつ)
- 乳腺炎(にゅうせんえん)
- 無乳症(むにゅうしょう)
といったものがあります。
ひとつずつ解説していきましょう。
異常な出血
出産時に少しの出血があることは普通ですが、
出産が終わったのにずっと出血が止まらない
といった状態になってしまうと、それは異常な出血です。
出血してしまう原因はいろいろありますが、症状がひどく出血が止まらないような最悪の事態になってしまうと、卵巣と子宮を摘出しなければいけなくなることもあります。
子癇(しかん)
出産後、
母猫の血液中にある「カルシウム」の量が少なくなって、”けいれん”が起きてしまうことがあります。
出産後1~3週間までに起こることが多いようですが、授乳中の期間であればいつでも発症する可能性があります。
原因としてはハッキリしていませんが、
子猫の数が多くて母乳と一緒にカルシウムが出てしまうことが関係している
とも言われています。
症状が出てしまった場合は、命を落としてしまうこともあるのですぐに動物病院へ連れて行き適切な治療を受ける必要があります。
子宮内膜炎・子宮蓄膿症(しきゅうないまくえん・しきゅうちくのうしょう)
出産後、
子宮に細菌が感染してしまうことにより発症する病気です。
- 発熱
- 食欲の低下
- 陰部から腐敗臭がする
といった症状があらわれます。
難産になってしまったことや胎盤が排出されなかったことなどが原因となるようです。
ひどくなると子宮内に膿が溜まってしまう「子宮蓄膿症」になってしまい、
さらに進行すると子宮が腫れあがって
- お腹が膨れる
- 陰部から膿が出る
といった症状が出ます。
命の危険がある病気なので、症状が見られたらすぐに動物病院へ連れて行きましょう。
産褥熱(さんじょくねつ)
出産のときに
子宮や膣内の粘膜に傷がつき、細菌に感染してしまい高熱が出てしまう病気です。
悪化してしまうと、
- 「子宮内膜炎」
- 「腹膜炎」
- 「敗血症」
といった病気になることもあるので注意しましょう。
乳腺炎(にゅうせんえん)
乳腺炎は、
母猫の乳腺が何かの原因により、炎症を起こしてしまう病気です。
- 乳房が腫れてしまう
- しこりができる
- 発熱
といった症状が出ます。
また、痛みが出るので授乳をイヤがるようになります。
原因として
「子猫があまり母乳を飲まないことで、母乳が体内に溜まる」
「乳房が傷ついて細菌に感染してしまう」
といったことがあげられます。
子猫の授乳に影響も出ますし、何より細菌に感染していた場合は母乳に細菌が含まれてしまうことになるので、子猫にも危険が及びます。
症状が見られるようならすぐに動物病院へ連れて行きましょう。
無乳症(むにゅうしょう)
出産後、
母乳が分泌されない状態になってしまうことを「無乳症」といいます。
子猫が母乳を飲もうとしてもまったく出てこないため、お腹を空かせてニャーニャー鳴き続けてしまうようになります。
動物病院で治療をおこない、間接的に母乳の分泌を促すと同時に、子猫にはとりあえず飼い主さんがミルクを与えるようになります。
まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は「飼っている猫が妊娠・出産をするときに飼い主にできることと、猫が出産した後になりやすい病気や症状」について解説させていただきました。
内容をカンタンにまとめると
- 飼い猫が妊娠したことに気づいたら動物病院で診察を受ける
- 妊娠中は多量のエネルギーが必要なので、栄養価の高いごはんをあげる
- 猫に安心して出産してもらうために環境を整えておく
- 出産時にはあまり手を出さない
- 難産など何かトラブルが発生したときには動物病院へ連絡して指示を仰ぐ
- 出産後にはなりやすい病気や症状があるので気をつける
といったところでしょうか。
生まれてくる子猫はとてもカワイイですが、それに伴う責任も増えます。
大切な家族(猫)が生んだ小さな命です。
無下に扱うようなことはしないようにしてください。
それでは、この記事が少しでもあなたの参考になったなら幸いです。