
こんにちは!こんばんは!クロネコあぐりです。
この記事では
猫がヒートショックになる原因と自分でやれる対策方法
について触れてるニャ!
みなさん
「寒暖差で起こる危険って何か分かりますか?」
そう!
「ヒートショック」
です。
よく聞くのは、冬場にお風呂に入ろうとしたら心筋梗塞を起こして亡くなられてしまうお年寄りの話とかでしょうか。
じつはあのヒートショック、
猫などの動物でも十分に起こる可能性のある危険なことなんです。
しかも
冬は当然のことながら”暑い夏の時期”にも起こる可能性があるんです。
人間のことばかり話題になるのであまり考えたことない方も多いと思いますが、寒暖差の激しくなる時期には「猫のためのヒートショック対策」もしっかり考えてあげないといけません。
ということで今回は
- 季節は関係ない?猫も発症してしまう「ヒートショック」
- 夏も冬もこれが危ない!猫のヒートショック3つの原因
- 猫にヒートショックを起こさせないための3つの対策
について解説させていただこうかなと思います。
「防げるはずのリスクを自分のせいで防げなかった」なんてことがないように、しっかりと対策を考えてあげるようにしましょう。
- 季節は関係ない?猫も発症してしまう「ヒートショック」
- 夏も冬もこれが危ない!猫のヒートショック3つの原因
- 猫にヒートショックを起こさせないための3つの対策
- ヒートショック以外にも注意!”加湿”も忘れずにしよう
- まとめ
季節は関係ない?猫も発症してしまう「ヒートショック」

「ヒートショック」とは
大きな温度変化によって血圧が急激に上下してしまい、心臓や血管に負担がかかりダメージを受けてしまっている状態
のことを言います。
一般的には”温度差が10℃以上あると危険”とされていて、特に心臓や血管の弱い「高齢のシニア猫」「子猫」「持病のある猫」は発症の危険が高いので注意が必要なのニャ!
つまり、冬場など寒い時期のイメージがあるヒートショックですが、暑い時期でもクーラーなどをつけることにより生じる寒暖差で
冬だけではなく夏でも発症してしまう可能性があります。
猫がヒートショックになるとどんな症状が出るの?

猫がヒートショックを発症してしまうと、
- 心筋梗塞
- 呼吸困難
- 視点が定まらずふらつく
- 脚がしびれたようになり立てなくなる
- 下痢や嘔吐
といった症状が見られるようです。
基本的には人間が発症してしまったときとあまり変わらないようですね。
ただし、下痢などの一部の症状だけの状態だと
「冷えてお腹壊したのかな?」
程度にしか思わず、ヒートショックになっているのを見落としてしまうこともあるので見極めには注意が必要です。
夏も冬もこれが危ない!猫のヒートショック3つの原因

猫がヒートショックを発症してしまうのはどんなときにどんな原因があるのでしょうか?
続いてヒートショックの原因を調べてみました。
猫がヒートショックを発症する主な原因としては
- 家の中の行動範囲内で寒暖差の大きい場所がある
- 普段は室内飼いだが散歩などで外に出ることがある
- シャンプーをする
といったことがあげられます。
ひとつずつ解説していきましょう。
家の中の行動範囲内で寒暖差の大きい場所がある
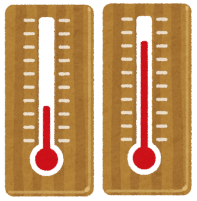
家の中はエアコンが効いているからと油断していませんか?
最近では夏場の気温の上昇が激しく、38℃~40℃といったかなりの猛暑日になることも珍しくありません。
そんな日にはどうしてもエアコンの設定温度が低くなってしまうものですよね。
たとえ温度を28℃に設定していたとしても、すでに10℃以上の寒暖差を作ってしまっていることになるのでヒートショックを発症する条件はそろってしまっています。
夏場はどうしても熱中症や脱水症状の方が起こりやすくそっちに気を取られがちですが、ヒートショックの可能性も十分に考慮して家の中であっても寒暖差の少ない環境をつくってあげるようにしましょう。
家の中には風が遮られて意外と温度が変わっていないところがあります。
特に、隅っこで何かの陰になっているようなところは”猫が好みやすいが暖房が効きにくい”といった悪条件が重なってしまいます。
しかも、そういった場所に猫のトイレを設置してしまっていることが多いようです。
また猫ベッドを窓際に置いているような場合、日中は陽が当たって暖かいが夕方以降は急激に冷えるため温度差が激しくなるので注意が必要です。
普段は室内飼いだが散歩などで外に出ることがある

猫を飼っている方の中には
「普段は完全室内飼いだけど、運動や気分転換のために外に散歩に連れていく」
ということをやられている方がいます。
しかし、冬場だけではなく夏場でも、
「エアコンの効いた室内から外に出る」
「外からエアコンの効いた室内に入る」
といったことは温度差がとても大きくなりやすい行動です。
温度差が大きくなればなるほどヒートショックを発症してしまいやすくなりますし、散歩をすれば少なからず運動をしていることになるので、余計に心臓や血管に負担をかけることになります。
散歩をさせることは悪いことではないけど、外と中の温度差が大きい時期には注意が必要になってくるのニャ!
シャンプーをする

- 「散歩から帰ってきたら脚を洗ってあげている」
- 「毛の長い猫で汚れやすく、定期的にシャンプーをしている」
など、猫もお風呂場を使うことがあります。
しかし、お風呂場は家の中でもいちばん寒暖差が大きくなりやすい場所で人間でもいちばんヒートショックが起こりやすい場所です。
しかも夏場は暑いために水を、冬場は寒いためにお湯を使うため急激に冷やしたり温めたりしてしまうことが多いので注意が必要です。
猫はもともとキレイ好き。
自分で毛づくろいをしていつも体をキレイに保っているので、シャンプー自体あまりする必要はないのニャ!
猫にヒートショックを起こさせないための3つの対策

猫がヒートショックを発症してしまう主な原因がわかったところで、次はそれに対する方法を解説していきましょう。
ちょっとした心がけで発症してしまうリスクを大きく下げることができるので、ぜひやってみてください。
猫の寒さ対策をするときは下から、夏は特定の部屋だけ冷やさない
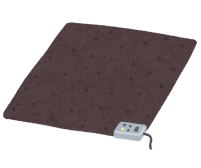
猫は自分たち人間より体も小さく、また四足歩行であるため地面に近い場所でいつも行動していることになります。
しかし、エアコンで暖められた空気は部屋の上に溜まっていきます。
「寒くはないんだけど足がとても冷たくなってる」
といった経験はないですか?
その冷たくなってる足の位置、猫からすると全身がその位置にいるんです。
つまり、
人間がエアコンで暖かいと感じていても猫からすれば寒いと感じていることがある
ということです。
なので、猫のための寒さ対策をするときには
- ホットカーペットを敷いてあげる
- エアコンの風は下に向けて床の方から暖めていく
といった感じで下に意識を向けてあげると良いでしょう。
※ホットカーペットなどは長時間居続けると低温やけどを起こしてしまう危険もあるので注意しましょう。
また、夏の時期の場合には特定の部屋だけエアコンが効いているといった状況を作らず、猫が行く可能性のある他の部屋や廊下など家の中全体がなるべく同じくらいの温度になるよう工夫しましょう。
散歩に連れて行くときは体を慣らしてから出かけよう

「暖かい室内からすぐに寒い外に出る」
「涼しい室内からすぐに暑い外に出る」
といった行動は心臓や血管の負担が大きくなりやすく、ヒートショックになりやすいです。
なので、外に出るまでに1段階踏むようにしましょう。
具体的には
外と中の温度の境目になる「玄関」に数分いてもらい外気温に体を慣らす時間を作る
といったことですね。
急激な寒暖差が危険を招くので、緩やかにしてあげて回避しましょう。
また、
「冬場であれば気温の上がる日中」
「夏場であれば気温の下がる朝や夕方」
といった時間帯に行き、なるべく温度差が無いように工夫してあげるのも良いでしょう。
お風呂場を使うときは事前に暖め、シャワーの設定温度に気をつける

家の中でいちばん寒暖差の激しい場所だと思われる「お風呂場」
しかし、事前にしっかり準備をしておいてあげればなんの問題も無く猫をキレイにしてあげれます。
方法はカンタン!
猫を入れる前に温かいシャワーでお風呂場の中の空気を暖めてあげる
これだけしておけばリスクは大きく下がります。
最近では、お風呂場を事前に暖める「浴室暖房」などもあるので、飼い主さん自身のリスク回避のためにも検討してみていいかもしれません。
※こちらは取り付け工事不要なタイプです。
また夏の暑い時期の場合、暑かっただろうからとつい冷水で洗ってしまいがちです。
洗うときのシャワーの温度はぬるま湯くらいの温度にして、最初は心臓から遠い脚先からかけるようにすれば良いでしょう。
当然、終わったあとはすぐにタオルで水気を取ってあげることも大切ですよ。
ヒートショック以外にも注意!”加湿”も忘れずにしよう

夏場はまだいいですが、冬場になるとエアコンなどの暖房をつけた場合にどうしても空気が乾燥してきてしまいます。
人間でもそうですが、猫も部屋の空気が乾燥していると様々なトラブルが発生する恐れがあるんです。
例えば
- 皮膚のトラブル・・・乾燥によって皮脂が少なくなると「痒み」「赤み」「フケの増加」「脱毛」「肉球のひび割れ」といった症状が出ることがある
- 呼吸器のトラブル・・・呼吸のたびに鼻や喉の粘膜から水分が失われることによってダメージを受けたり、「猫喘息」などの発症、悪化につながることがある
- 感染症のリスクの増加・・・空気が乾燥していると鼻や喉の粘膜のバリア機能が低下してしまうため、ウイルスや細菌が体内に侵入しやすくなる
- 脱水症状になるリスクの増加・・・もともと水をあまり飲まない猫は空気が乾燥していると喉が渇きやすくなるなど、体内の水分が減少しやすくなるため脱水症状になるリスクが高くなる
といったようなことですね。
そのため、部屋の加湿をしてあげることは猫の健康を維持するのに必須と言えるでしょう。
猫が快適と感じる部屋の湿度は50%~60%
40%以下だとトラブル発生の危険が出てくるし、60%を超えてしまうと不快に感じ、ダニやカビが発生しやすくなってしまうので注意が必要ニャ!
まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は「猫も発症するヒートショック」について原因や対策法などを解説させていただきました。
今回の内容をまとめると
- ヒートショックとは「大きな寒暖差で心臓や血管に負担がかかりダメージを受ける」状態のことで冬だけではなく夏にも起こる可能性がある
- 猫がヒートショックになると「心筋梗塞や呼吸困難」「ふらついたり立てなくなる」「下痢や嘔吐」といった症状が出る
- 猫がヒートショックになる主な原因には「家の中の寒暖差」「散歩での寒暖差」「シャンプーのときの寒暖差」がある
- 猫のヒートショック対策として「寒さ対策は下の方からする」「散歩の前には体を慣らす」「シャンプーの前にお風呂場を暖める」といったことが効果的
- 暖めるだけでなく加湿を忘れないようにする
といったところでしょうか。
人間だけではなく猫でも発症してしまう危険のある「ヒートショック」
一見してヒートショックだとわからない状態のときもあるようなので、普段から注意して何か異常があればすぐに気づけるようにしておきたいですね。
それでは、この記事が少しでもあなたの参考になれば幸いです。