
こんにちは!こんばんは!クロネコあぐりです。
この記事では
猫から人に感染する病気と感染を予防するためにできること
について触れてるニャ!
猫好きのみなさん
「野良猫を見かけたら...触りたくなりますよね?」
自分も猫を飼っているけど、外で見かけることがあるとついつい触りたくなってしまいます。
でも、気をつけてください。
猫がかかる感染症の中には人間にうつってしまう病気もあるんです!
猫に限らず、動物から人へ感染する病気のことを
「人獣共通感染症」
または
「Zoonosis(ズーノーシス)」
と言うのですが、この”人獣共通感染症”の中には命を落としてしまった例もあるとても危険な感染症もあるんです。
しかしこの人獣共通感染症は”感染症法に定められた病気ではない”ので十分な対策も取られていないのが現状です。
となれば、どんなものか知らないよりは知っている方がいいですよね。
そこで、人獣共通感染症の中でもかかりやすいものや代表的なものを感染源ごとにいくつか紹介していきたいと思います。
ということで今回は
- 猫から人にうつる「人獣共通感染症」の主な病気13種
- 感染を予防するためにできること
について解説させていただこうかなと思います。
「敵を知り己を知れば、百戦危うからず」
と言いますし、知っておいて損はないでしょう。
ちなみに、猫がかかりやすい病気についてはこちらで詳しく解説しています。
猫から人にうつる「人獣共通感染症」の主な病気13種

猫から人にうつる病気にはさまざまなものがありますが、
その主な感染源は
- 細菌
- 真菌(いわゆるカビ)
- 原虫(単細胞の微生物)
- 寄生虫
といったものがあります。
それでは、感染源ごとに紹介、解説していきましょう。
細菌が感染源の病気

まずは、細菌が原因の病気です。
猫ひっかき病
猫を飼っている人なら一度は聞いたことがある病気ではないでしょうか。
この病気は「バルトネラ菌」という細菌をノミが媒介となって猫に感染します。
しかし、この病気は猫が感染しても何も症状が出ないので、普段の生活から猫が感染しているかどうかを見抜くのはとても難しいです。
- 感染した猫にひっかかれる
- 感染した猫に咬まれる
- 猫についていたノミに刺される
- 傷口が腫れる
- リンパ節が腫れたり、痛みが出る
- 発熱
猫にひっかかれたり、咬まれたりした後、
3日~10日程度の潜伏期間
を経て症状が現れます。
ほとんどの場合は自然に治っていくようですが、まれに重症化してしまうこともあります。
ひっかかれたり、咬まれたりしたときは軽く考えずにしっかり傷口の消毒をするのニャ!
また、室内飼いの場合でも普段から猫のノミ駆除を徹底しておいた方が良いのニャ!
パスツレラ症
「パスツレラ菌」という細菌が原因となる病気です。
猫の口の中や爪にいる細菌ですが、「常在菌」と呼ばれる菌で
健康的な猫の口の中で100%、爪で25%くらい保有率があります。
そのためこの細菌に猫が感染しても何も症状が出ませんが
人が感染すると重症化することがあり、さらには”命を落としてしまった”
例もあります。
特に
- 「糖尿病」「肝臓障害」といった基礎疾患のある人
- 「高齢者」「体力が低下している」といった抵抗力の弱まっている人
の場合は重症化する可能性が高いので注意が必要です。
- 感染した猫に咬まれる
- 感染した猫にひっかかれる、
- 気道感染
- 傷口の痛み
- 傷口の腫れ
- 気管支炎や肺炎(気道感染した場合)
年齢が”40歳以上”の方に発生することが多く、
感染してから数時間後に傷口の痛みと腫れが出てきます。
ひどくなると「骨膜」と呼ばれる骨を覆っている膜が”壊死”を起こしてしまうこともあるので気をつけるのニャ!
猫に咬まれたり、ひっかかれたりしたらすぐ消毒をするようにしましょう。
また「ズキズキとした激痛がある」といった症状が出たら早めに病院へ行きましょう。
サルモネラ症
「サルモネラ菌」が原因で起こる病気です。
主に、
- 「豚、鶏、牛などの腸内」
- 「汚染された土壌、水、食物など」
に生息し、特にミドリガメなどの爬虫類は持っている確率が高い細菌ですが、猫も持っていることがあります。
大人の猫が感染した場合は症状が出ないことが多いですが、子猫が感染すると「下痢や嘔吐」などの症状が出ることがあります。
人の場合、”健康な成人”であれば症状が現れることはないようですが、”子どもや高齢者”だと少ない菌でも症状が出てしまうことがあるようです。
- 「菌を持っている猫、またはそのウンチ」に触れた後に、
何かの原因で口の中に菌が入ることによって感染してしまう
- 下痢
- 嘔吐
- 急性胃腸炎
感染した場合、”8時間~48時間の間”に発病することが多いです。
子供が感染してしまった場合、意識障害や痙攣など重症化しやすいので気をつけましょう。
猫のウンチを始末した後などにはしっかりと手洗いをするように心がけるのニャ!
カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症
「カプノサイトファーガ・カニモルサス」という細菌が原因の病気です。
この菌は、猫の口の中の常在菌で国内の猫もほとんどの猫が持っている細菌ですが、猫には何の症状も出ません。
病気を発症することはほとんどないのですが、もし発症してしまった場合、
”致死率が高く危険な病気”
です。
- 猫に咬まれる
- 猫にをひっかかれる
- 目、口といった粘膜部分や傷口をなめられる
- 発熱
- 腹痛、頭痛
- 倦怠感や吐き気
重症化してしまった場合、
- 「敗血症」
- 「骨髄炎」
- 「多臓器不全」
になってしまい命を落としてしまうこともあります。
体調不良のときなど”抵抗力が弱っているとき”や高齢者、基礎疾患のある人など”免疫力が低下している人”は注意しておいた方が良いのニャ!
普段から咬まれたり、ひっかかれたりした場合は消毒するようにしましょう。
また、カワイイからと安易に顔周りなどをなめさせないようにした方がいいです。
真菌(カビ)が感染源の病気

続いて、真菌(カビ)が感染源の病気を解説します。
皮膚糸状菌床(ひふしじょうきんしょう)
「皮膚糸状菌」という菌が原因となって起こる皮膚の病気で「猫カビ」とも呼ばれることがあります。
「免疫力の低い子猫やシニア猫」
「ペルシャ猫のような毛の長い猫」
に起こりやすい疾患で、顔や足などの感染したところに円形の脱毛と痒みが起こり、周囲にフケが出るようになります。
人に感染した場合、多くの人は感染しても症状が出ないのですが、
「子供や免疫力の低くなっている人」
「皮膚の弱い人」
などは症状が出てしまうことがありますので注意が必要です。
- 皮膚糸状菌に感染した猫を触る
- 「猫用ブラシ」など猫に使った道具などを触る
- 痒み
- フケ
- リング状に炎症が起こる
感染した場合人から人、人から物へと感染していきますので、症状が見られたら早めに病院へ行くようにしましょう。
原虫が感染源の病気

次は原虫が感染源となる病気を紹介します。
原虫とは単細胞の微生物のことで、一般的によく聞く
「ゾウリムシ」
「アメーバ」
といったものの仲間です。
ある種の原虫は人や動物に寄生して重い病気を引き起こしたりします。
トキソプラズマ症
「トキソプラズマ・ゴンディ」という原虫が原因で、猫に関わりが深い病気です。
というのも、この原虫は他の動物にも感染しますが、
猫の体内に入ったときだけ増殖していく
という特徴があります。
つまり、他の動物の体内に入っても増殖せずじっとしているだけなのです。
こういう”寄生虫にとって居心地がよく増殖できる動物”を「終宿主」と言い、トキソプラズマの終宿主は猫だということです。
その後、猫の体内で「オーシスト」と呼ばれる卵のようなものができ、ウンチと一緒に外へ出されます。
ただし、
1度トキソプラズマに感染した猫は抗体ができるため、オーシストができることはありません。
- 猫のウンチと一緒に出てきたトキソプラズマが何かの原因で口に入ったりすることで感染
- 発熱
- リンパ節の腫れ
- 視力障害、眼の痛み(目に発症した場合)
多くの場合、何も症状は出ないのですがこういった症状が出ることがあるようです。
抗体を持ってない妊婦さんが感染すると、
「流産や死産」
「生まれた子供に先天的な障害が出る」
可能性もありますので十分注意しましょう。
またトキソプラズマにはちょっと面白い話もありますので、興味のある方はこちらも読んでみてください。
クリプトスポリジウム症
「クリプトスポリジウム・パルバム」という原虫が原因の病気です。
猫以外にも多くの動物の消化管に寄生しています。
クリプトスポリジウムは”塩素に抵抗力がある”ため、過去には水道水から集団感染が起きたこともあるようです。
猫が感染しても症状は何も出ません。
- 感染した猫のウンチに含まれたクリプトスポリジウムが、何かの原因で口に入ることで感染
- 腹痛を伴う激しい水のような下痢
- 発熱
- 嘔吐
感染して”2日~5日で症状が現れる”ようです。
ただし、この病気に感染した場合の有効な治療法は今はまだないそうなのニャ!
なので対処療法をしながら自然治癒を待つことになるのニャ!
寄生虫が感染源の病気

寄生虫が感染源の病気もさまざまなものがありますが、大きく分けて
- 外部寄生虫が感染源
- 内部寄生虫が感染源
の2種類に分けられますので、種類別に紹介していきましょう。
外部寄生虫が感染源の病気
ノミやダニなど体の外側に寄生する虫が原因の病気です。
ノミ刺咬症
猫についたノミなどは人にもうつります。
普段から外への出入りを自由にしているなら、ノミやダニの駆除は徹底しましょう。
- 猫についたノミがうつって刺される
- 痒み
- 刺された部分の腫れ
ライム病
”マダニ”によって媒介される
「ボレリア菌」
という細菌が引き起こす感染症です。
- 猫についたマダニが人をかむことによって感染
- 筋肉痛や関節炎
- 発熱
- 悪寒
症状として”インフルエンザに似たような症状”が出ます。
その後、ひどくなると
「皮膚炎」
「心疾患」
などを起こすこともあります。
疥癬(かいせん)
「猫ショウセンコウヒゼンダニ」というダニによって引き起こされる皮膚の感染症です。
- 猫ショウセンコウヒゼンダニに寄生されている猫に触れることによって感染
- 激しい痒み
- 水疱
- じんましんのような腫れ
感染したときにはひどいですが、ほとんどは重症化することなく自然治癒するということです。
ツメダニ症
猫に寄生した
「ネコツメダニ」
という白くて小さいダニが引き起こす皮膚疾患です。
- ネコツメダニに寄生された猫を抱きかかえるなどで触れることによって感染
- 強い痒みや痛み
- 発疹
- 皮膚炎
猫が感染してしまった場合は治療が必要ですが、
人が感染した場合は自然に治ることが多いということです。
内部寄生虫が感染源の病気
回虫など体の中に寄生する虫が原因の病気です。
猫回虫症
「回虫」というおなかの中の虫によって引き起こされる感染症です。
人の体内に侵入した場合は成虫になることはできず、幼虫のまま体内を移動して内蔵や目などにさまざまな障害を起こします。
これを「幼虫移行症(トキソカラ症)」と言います。
- 感染した猫のウンチと一緒に出された回虫の卵が何らかの原因で口の中に入った場合に感染
症状は内蔵に移行する「内臓移行型」と目に移行する「眼移行型」に分かれます。
「内蔵移行型」
- 発熱
- 筋肉痛や関節痛
- 肝障害
「眼移行型」
- 視力低下
- 失明
また、”脳”に移行してしまった場合は
けいれんなどのてんかん発作を起こす
こともあります。
猫では症状が出ないことがほとんどだけど、子猫の場合には「下痢」などの消化器官の症状が出ることもあるのニャ!
瓜実条虫症(うりざねじょうちゅうしょう)
「瓜実条虫(サナダムシ)」という虫によって引き起こされる病気です。
”人に感染することは非常にまれ”だといわれていますが、子供などは気をつけるようにしましょう。
- 瓜実条虫の幼虫が潜んだノミを飲んでしまう
- ノミを潰したりした際に、手についた幼虫が口に入ってしまう
- 腹痛
- 下痢
大人が感染してもほとんどが何も症状が出ないですが、子供では症状が出ることがあります。
感染を予防するためにできること
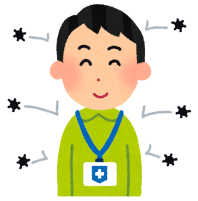
猫から人へ感染する病気があるとはいえ、
普段の生活からきちんと予防しておけばそれほど感染を気にすることもありません。
ということで、猫と生活していくうえで気をつけておくことを解説していきます。
ノミやダニの駆除はきちんとしよう

完全室内飼いの猫でも
人にくっついて家の中に侵入し、猫に寄生する
こともあります。
油断しないように定期的なノミやダニの駆除を行うようにしましょう。
猫に咬まれたり、ひっかかれたりしたらすぐに処置をしよう

猫に咬まれたり、ひっかかれたりした場合は、
軽く考えずにすぐ傷口の消毒
などをして処置するようにしましょう。
特に小さい子どもなどは”抵抗力が弱い”ので、
腫れなどが見られたときは病院に行くようにしましょう。
猫の世話をした後は手を洗うようにしよう

細菌などの病原体は、
手についたものが顔周りを触ることによって口や目から体内に入ってしまう
ことが多いです。
なので、猫のトイレを掃除した後などは
必ず”石鹸”や”ハンドソープ”などを使い手を洗う
ようにしましょう。
猫と一緒に過ごす環境はキレイにしよう

猫と一緒に過ごすところはこまめに掃除をするなどして
常に清潔にしておく
ことを心がけるようにしましょう。
汚れた環境では”人だけではなく猫にもストレスが溜まってしまい”
病気を発症する要因にもなりかねません。
まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は「猫から人に感染する可能性のある病気」について解説させていただきました。
猫から人へ感染する病気って結構あるものですね。
猫はカワイイですし、ついつい触りたくなる気持ちはわかりますが、触った後やひっかかれてしまった後(特に野良猫)はきちんとした処置をすることが重要ですね。
猫から病気が感染したとなったら、
「猫が悪者扱い」
みたいになってしまいがちですが、
猫自体は感染を防げませんし、感染を予防する環境づくりもできません。
飼い主さんが普段から気をつけて人のみならず猫の健康も守るように心がけていきましょう。
それでは、少しでもこの記事が参考になったなら幸いです。